|
注意:下に行けば行く程、映画の詳しい内容が明らかになります。また、評論のような真面目な感想は書いておりません。
まだ映画の内容を知りたくないという方や、ふざけた感想なぞ読みたくない方は、これより下にお進みにならないで下さい。
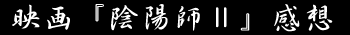
★全体
前回、「あれ」で当たりましたので、説明を省いてネタを変えましたが、雰囲気その他背景諸々はそのままでまた映画にしてみました〜な、内容。主要スタッフ、キャストに変更がないので当然なのですが、話に意外性がなく、主要部分にロクに変化がないのもちと詰まらぬような気がします。
★安倍晴明
前回の真田さんとのアクションも見せ場でしたが、今回はその立ち回りが増えています。鬼(未満)相手に一回、幻角(中井さん)相手に二回。狩衣の袂をばっさばっさと活用しながらの立ち回りは野村萬斎『陰陽師』ならではかと。
呪術に長けた「陰陽師」という役と凄い矛盾している気がしますが、カッコ良いので、許します。
★源博雅
今回は多少お役立ちでした。勿論、「笛」でしか役に立たないのは当たり前。前回に比べて、自分の存在意義、その「能」をよく解ったキャラクターになっておりました。
伊藤さんもコメントにも同じような事を言われてました。
つか、この人、一応武人の殿上人じゃなかったけ…。何で、立ち回りシーンは全て晴明の役割なんだ。
☆幻角
中井さんはちと悪役としての凄みに欠けます(特に口調)が、アクションはなかなかでした。
初めの方で人々を助けていた理由の説明がなかったのですが、あれは都を潰そうとするその後の行動に非常に矛盾します。名を広め、朝廷に味方となる人物を見つけて、相手方の動向をチェックしやすくするため?それとも、その後に自分が君臨しやすくするため?
よー、解りません。
(もしかして、ただ単に生活費のためだったのか…?)
三角お帽子の下にひょっこりと角が生えているのではと期待したのですが、違いました。
★蜜虫
今回は蝶が少なく、今井さん出ずっぱりでした。
おうむ口まね晴明の台詞繰り返しだけじゃなくて良かったね。相撲取り相手に動き回ったり、あちこち走ったりしたから下に裾を絞った袴を履いていたことを今回初めて知りました。前回はどうだったんでしょう。原作の蜜虫はもっと大人の女性のような(人格すらないような)式神なんですが、映画では一貫して子供っぽいです。
★日美子
映画で深田恭子さんを見たのはこれが初めてです。
藤原安磨呂の娘として育てられているが、実は…。という男勝りな姫君の役。髪型と顔のマッチングはともかく、衣装がなかなかに良かったです。あと、これ宣伝されてなかったと思いますが、上半身ヌード(映るのは背中のみ。胸の谷間のアップもあるがあれが本当に深田さんのかどうかは不明)のシーンがありました。
いきなり現れては普通の的に向かって矢を射ているだけで、設定を生かした立ち回りもなく、折角の男勝りはロクに活用されませんでした。(わざわざの男勝りは20歳過ぎても売れ残っている理由だったか?←18年前の映像で3〜5歳くらいに見えたので、日美子さんは21〜23歳なんですよね。これ平安においては売れ残り)
萬斎さんとの絡みは前回のキョンキョンの方が絵的に色っぽかったです。(萬斎ファンからの視点)
最後のシーンで顔が白塗り、だけど首はそのままなのが異様に目立ちました。(首も塗ってあげて下さい)喋りが不自然なのは、初時代劇故に仕方ないんですかね。(まあ、今井さんも同じようなものですが)
★須佐
名前を見た時点で少々神話を知る人なら、彼の役割が丸判りだと思います。
特殊メイクばかりでちょっと気の毒でした。日美子との○○っぷりは巧かったです。
★月黄泉
月読じゃなくて、この「黄泉」なんですね。(名前だけ見たら、日美子、須佐と兄弟かと思うよなあ)
骸骨に晴明が「舌」を与えて喋らせたら、古手川祐子さんが出て参りました。つまり幽霊さんです。
キョンキョンは早良親王を止められましたが、彼女は幻角を止められませんでした。つまり、報復希望暴走男を止めるなら、若いうちにのようです。月黄泉さんも人魚の肉を食べておくべきだったかもしれません。
★時代考証
も、どうでもいいです。
★術系
今回は一人で見に行ったので、解説が得られませんでした。また現代の陰陽師のご指導があったようなので、間違いはないでしょう。使用される「出雲八卦」は映画用の創作もの(でっちあげ)だそうです。
★物語★
−説明なしで−
前回、必要な設定は説明してしまったのでさっさと始まります、陰陽師第二段。
日が陰って以来、都に鬼が出没し、人々を喰らうようになった。そのため、鬼封じの儀式を兼ねた宴が藤原安麻呂の館で催される。源博雅はそこで男勝りの安麻呂の娘日美子を知る。
彼女は日が陰った時より夜な夜な寝所を抜け、さ迷い歩くようになっていた。しかし、翌朝尋ねても彼女は自分が歩き回っていたとは知らない。その娘の行動に不安を覚えた安麻呂は博雅を通じて晴明に娘の事を尋ねるが、晴明は鬼との関わりはないと告げる。
娘の夢遊病を心配するよりも、小動物の怪我をたちまちのうちに治す方がよほど驚きだと思うのですが、父安麻呂、そっちは全然気にしておりません。(一応、話題にはなる)定番通り、博雅が日美子にホの字になるのですが、今回は会う度ににやけているだけで、それ程その気持ちが活用されることはないです。
−幻角、須佐−
またその頃、巷では身分の格差に関わらず誰の怪我をも治癒する「幻角」という人物が神の如くあがめられていた。この時代、貴族は雅びに暮らすが、そうでない人々の生活は苦しい。
一方、博雅は夜道で心を打つ琵琶の音に出逢う。音に惹かれて笛を吹き、琵琶を奏する「須佐」と心を交わす。しかし、彼は自分が弾く曲の詳しいいわれを知らなかった。
あがめられているシーンはありますが、あんまり「神」っぽく扱われておりません。拝まれて感謝されているだけです。供え物もなし。また先にも書きましたが、彼が人々を治療している理由が判らないのです。以前の道尊もそうでしたが、じっくりとした役作りが出来ておりません。今回は一応、悪者になる理由だけは明らかにされていました。(道尊の時は何の説明もなかったよな…)
須佐については特に矛盾なく。琵琶「玄象」の話をもとにした登場の仕方は違和感ありませんでした。
−ア、アメノムラクモ!?−
宮中では鬼の出現と同調するかのように、天叢雲剣が鳴動する。
剣の調査を任せられた晴明は封印を解いた際に、アメノムラクモに引っ張られて宙を飛ぶ。怪異の理由が判らず、それは晴明の失態となる。それを機に、晴明をよく思わぬ反藤原氏の貴族たちは幻角に鬼を退治させ、鬼退治を命じられた晴明を失脚させようとする。
今回、最も驚いたのが、この剣の登場。
まあ、出雲ネタなら出すのが自然なのでしょうが、ええと、アメノムラクモこと、草薙剣(クサナギノツルギ)今では熱田神宮に納められていることになっているんですよね。一応、十二代の景行天皇の時に納められたとされているんで、平安時代に宮中にあるってのは…。
まあ、龍がデザインされている時点でかなりおかしいので、もうどうでもいいです。(ヤマタノオロチは漢字で八岐大蛇。即ち、「蛇」)
アメノムラクモに引っぱられ、ワイヤーで飛んで行く萬斎さんの動きは良かったです。
−鬼−
再び、鬼が現れ、人が喰われた。今度は左目。
鬼を射た矢じりより、晴明は鬼の手がかりを得るが、それは四つ頭の龍であった。貴族達に伴われて現れた幻角は晴明の「滅びる時は滅びる」という言葉に、一人頷き、何もせずにその場を去って行く。
その前夜、日美子は塀の外で倒れていた須佐を助ける。
このあたりは特にツッコミどころもなく。平安時代の姫様が見ず知らずの若い男を部屋に上げるのか?家人がそれを許すのか?と言ってもいいんですが、まあ、何でもありの「男勝り」ですから、止めておきます。
この時犠牲になった巫女さんがなかなか綺麗な女性でした。「能世あんな」さん。はじめて拝見するお名前ですね。チェックチェック。
−須佐と日美子−
笛を聞かせに、日美子のもとを尋ねた博雅はそこで須佐と再会する。ちょうど良いと琵琶と笛で須佐の村に伝わる調べを合奏するが、その音色に日美子は涙し、須佐は左腕の激痛に苦しみ逃げ出す。
逃げ出す須佐と娘の異変に、安麻呂はついに晴明に日美子の秘密を明らかにする。
彼女は実の娘ではなく、出雲族の生き残りであると…。
−出雲八卦−
アメノムラクモについて調べる晴明は、博雅のふとした言葉から鬼の真相に行き当たる。鬼は出雲八卦に従って、八人の神々の子孫を狙っている、と。晴明はタヂカラオノカミの子孫である力士から髪を奪い、蜜虫を使って罠を張る。が、鬼を封じた結界は鬼の正体に驚いた博雅によって破られ、鬼=須佐は彼らの前から姿を消す。
博雅が石を踏んでコケるシーンに劇場内からは素直な笑いが漏れました。(この作品では彼は完全にギャグキャラです)結界から逃れた鬼が晴明を襲うところで、陰陽師アクション!キュー!袖を振り回しながらくんずほぐれず。ちゃんと呪術を使いながら戦っているんですが、あれは運動神経が良くなくては絶対にできません。
あの当時の貴族に運動神経ね…。
−出雲がそんなに近いのか、と誰もが思った−
須佐は日美子の前に現れ、彼女に逃げろ、と告げる。
警告を受けた日美子は晴明のもとへ行き、自分の腕にある痣(あざ)を見せる。四方に伸びる四つの龍の形。
痣に秘められた秘密を悟った晴明は、日美子を伴って出雲族の村に向かう。
痣を見せるため上半身裸になる日美子なんですが、袖を捲れば十分に見られる位置にあるんですよね、痣。要はサービスショットですよね。分かってますって。深田さんのお色気(を狙っているらしい)あえぎもちゃんとあったし。ええ、分かってますとも。サービスには突っ込んじゃいけないんでしょう。(突っ込んでるがな)
そのヌードの
邪魔をしそうな博雅が晴明に術で固められて、よっこらしょっととマネキンのように動かされるシーンでもまた笑いが。
お笑いキャラおっけー。博雅のこういうシーンは割と楽しめます。
で、日美子を連れて出雲にさっさと着いている晴明に、「ええっ!出雲(島根県)ってそんなに近いの!」と(ちと古代史を知る人間の)誰もが思ったら、設定上、あれは都近くにある出雲族の村ということ。そんなん説明がなければ、分かりません。(誰かに喋らせるかなんなりしてくれよ)
−あー、やっぱスサノオですか−
タヂカラオの子孫を喰らい、残りはあと一人。その一人は須佐の実の姉である日美子…。
出雲族の村で母月黄泉は娘と晴明に真実を明かす。大和朝廷に村を襲われ、出雲族を皆殺しにされた復讐のために、父幻角は須佐を出雲の神「スサノオ」に捧げたのだ。日美子を喰らえば須佐は「スサノオ」になる。母は逃げてと言い、父幻角に連れられて現れた須佐も逃げろ、と言うが、鬼と人の狭間で苦しむ須佐に日美子は我が身を差し出す。
舌を失い喋られぬ骸骨に呪で舌を与えるシーンが良いです。普通に陰陽師を見た気がしました。しかし、やはりスサノオできましたか。でもって、「スサノオ」化した後の、デザインのモチーフは鱗たっぷりの龍。造りは悪くないんですが、「荒ぶる神」と言うよりは単なる「化け物」に見えました。う〜ん、カミサマらしく見せるのって難しいですね。
−み、巫女…−
幻角はスサノオと化した須佐とともに都を破壊していく。
一方、晴明はスサノオを封じられる唯一の存在アマテラスを天岩戸を開くことによって呼び出そうとする。
「これより先は神の領域。オレとてどうなるか知れぬ」
「お前が命を賭する時に、黙って見ているオレであると思うのか」
出雲族の村に駆け付けた博雅は晴明とともに神々の世界へと渡る。そして、天岩戸の前で博雅の笛に合わせ、晴明は舞を舞う…。
いやあ、もう、ここは萬斎さんの女装…、巫女姿でしょう。
天岩戸を開くためにアメノウズメの代わりをせにゃならんのは分かりますが…、踊るだけではなく、「女装」までするとは…。
しかも、白塗りの巫女…。
すみません。
退きました。
思いっっっきり、無茶苦茶退きました。
萬斎ファンとして許されないくらい退きまくりました。
あれは一歩間違えれば「お笑い」です。正直苦しかったです。見るのが辛かったです。早く終わって欲しかったのに、随分と長かったです。(辛さの余り長く感じただけかもしれません)
舞いはまあ、良かったのですが…。
はあ…。(溜め息)
ううっ、萬斎さんの女舞、楽しみにしてたのに…。(前回ですらちと苦しかった人間に、今回は無理があり過ぎた)
しかし、この段でやっと、唯一映画造りに関心するシーンがありました。それは天岩戸に昇っていく場面。この天岩戸に続く階段がかつて出雲大社にあったという物凄い長〜い階段だったのです。あれを見た時だけ「おおっ、これは!」と思いました。
…ええ、残念ながらそれだけです。
全体としてのつくりは前回に比べたらまとまりがありました。説明の必要がない分、ストーリーに力を入れたそうですが…、肝心の内容は、何だかひねりのない少年漫画のように見えました。
日本の映画はカネも時間もかけませんので、テレビで放送する特撮に毛が生えた程度にしか見えないのが哀しいです。あちこち手を入れて前回より綺麗に見せる努力はパンフで分かります(蝶(蜜虫)の動きは前回よりは自然だった)が、如何せん、晴明の家の庭からして「ウソくさい」。見ただけで、そこが平安の都であると納得し、映画の世界に没入していくことがどうしても難しいのです。人物が出来上がってしまった分、余計に「背景」が浮いてしまっているようにも思えました。未来の世界すら造り上げてしまう異国のCGに慣れた人の目には、あの「特撮背景」がどうしても「稚拙」なのです。
それが気になる人には楽しめず、気にならない人にはそこそこ楽しめる映画だと思います。あと、日本古代史に詳しくないのも必須かと。(ツッコミ入れたらキリがないから)
自分の総合評価は50点です。
役者80点。ストーリー50点。背景20点。
土曜日に行ったところ、映画館の席は1/6も埋まっておりませんでした。(前回は満席まであと一歩くらいだった。日曜日だったからだろうか)『陰陽師3』があるかどうかと言われれば、「ない」と答えるべきかと。
今の日本の映画界に「陰陽師」を満足に作るだけのカネも時間も力量もないことを惜しみます。(高望みできないって辛いよなあ…)
| ![]()